
BLOG
つくり手の言葉
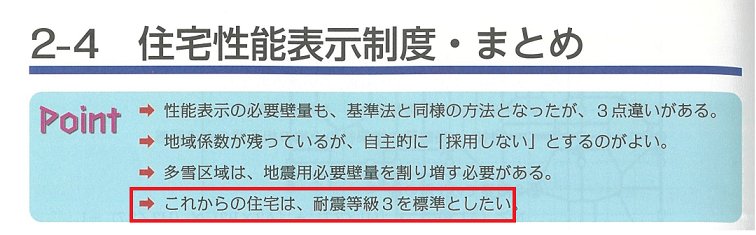
湿度が高い日が続きますね。
エアコンによる除湿が生命線です。
この時期だからこそ、ちゃんとドレンからお水が落ちているか、確認しましょう。
お水がまったく流れていないとなると、もしかしたらドレンがスライムで詰まっている事もあり得ます。
除湿したお水が排水できずに、室内機からポタポタ・・・なんて恐ろしいこと、あったりします。
気を付けましょうね。
さて、今日は出勤せずに、お勉強の日です。
というのも、建築士の定期講習。
建築士は、3年ごとに登録講習機関が行う一定の講習を受ける義務があります。
今どきはオンラインで講習から終了考査まで対応可能なんですけど、建築士の勉強に通った学校に顔出しも兼ねて、オフライン講習。
てな訳で、今回は建築士の定期講習って、どんなの?って話。
さて、講習は丸1日かけて行います。
講習時間、5時間半。考査時間も含みです。
内容としては、建築基準法の基本体系や建築等に関する手続きなど基本を学びなおしつつ、度々変更される内容をさらっていきます。
十数年前に建築士を取得した後も意外と細かい所で変わっています。
ついつい当時勉強したことが頭に残ってしまってたりするので、アップデートです。
都市計画法、消防法、宅造法、省エネに関する法と多岐にわたります。
特に、昨年から今年にかけて、木造に関する建築基準法の大改正となりました。
省エネ基準の義務化、四号特例の範囲縮小。
これにより、どんな建物がどこまで申請が必要か、何を申請するべきか、かなり変わりました。
この辺りに、1時間くらいかけて解説です。
もちろん、普段から木造住宅を設計している私たちのような工務店は、改正前に準備して内容を理解していますが、建築士と言っても、すべての方が普段から木造や申請に関わっているわけではありません。
だから、定期講習でアップデート必要なんですよね。
その他にも建築士法に始まり、建築士の職業倫理や法的責任、行政処分についてや業務上のリスクまで、超早口でまくしたてられます。
講義終了後に考査試験があるので、皆必死でテキストにアンダーラインを引きまくります。
で、実は毎回この定期講習を受けるたびに思うのです。
省エネと居住環境と健康について、ほぼ同じ資料使いながら、ずーっと言ってるなって。
ふと思い立って、本棚を見てみたら、6年前のテキストがありました。
その頃から、もちろん、ZEHやBELS、HEMSによるエネルギーマネジメントの話は出ているし、室内温熱環境については、空気温度だけでなく、放射温度、相対湿度、気流速度が大事で、そこに代謝量や着衣量が影響するってことも、同じ文章、図柄。
快適な床温度は、19℃~29℃、くるぶしと頭の位置の温度差を3℃以内にすることが望ましいことも書いてある。
室温と知的作業効率の関係や、夏の日本のオフィスの設定温度が暑すぎることなど、ほぼ同じ。
つまり、どんな温湿度環境であれば、人が快適に、そして健康に暮らせるかの基本は語りつくされていて、建築士の資格を持っている者からすれば、繰り返し講義で伝えられてる事実です。
にもかかわらず、そこに注視しない家づくりはナンセンス・・・げふんげふん
ちなみに、同じく毎回繰り返し書かれている指標の一つに、
「耐震等級3」がある。
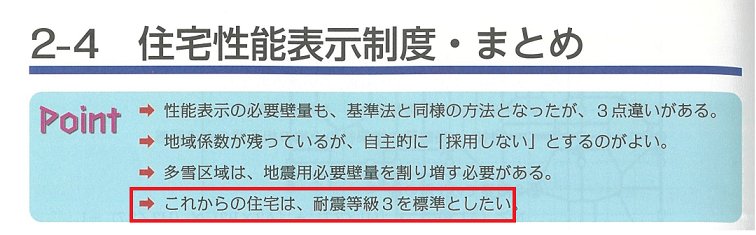
そう、建築士は、定期講習の度に、住む人のためには耐震等級3と言われ続けているのだ。
だから、建築士として設計している人たちは、ちゃんと居住環境にこだわり、構造計算をしてるんだなぁ。
なにせ、建築士の定期講習という、最も基本的な知識を得る場での内容なのですから。
そんな当たり前、場所での、当たり前の基準。
家を建てるご家族に、「必要ですか?」なんて聞くのもナンセンスですよね。
hiroyuki